DRONE INDUSTRY NEWSDRONE INDUSTRY NEWS
KIZUNA MATRICE
INSPECTION SYSTEM
INSPECTION SYSTEM
ドローン業界ニュース
-
 2026-01-31
2026-01-312026年1月AIドローンニュース ―AIが厳選した国内ドローン最新トピック集―
<NEWS 1|105機で“地域モチーフ”を夜空に> 宇部市/ときわ公園で105機ドローンショー(市制105周年) 【社会活用】 観光・文化×ドローンが定着へ。
市制105周年と公園開設100周年を記念したドローンショーを実施。105機がペリカン、テナガザル、市章などを夜空に描き、約15分間の演出で来園者を楽しませた。 https://news.yahoo.co.jp/articles/1c60025ba624bb2dd2282f3400af0a5718bb2134
<NEWS 2|河川上空を“災害輸送ルート”に> JR東日本など、板橋区で災害時想定のドローン物流(河川上空×CLAS) 【社会活用】 「災害時の物資輸送ルートとして運用できるか」を河川上空航路で検証
新河岸川を中心に設定したドローン航路で、水・食料/医薬品の輸送を想定して検証。CLAS対応で高精度な自動飛行・精密離着陸を目指し、技術面と運用面の両方を評価する。 https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2077852.html
<NEWS 3|演習場外で発見、破損なし> 陸上自衛隊都城駐屯地のドローン「蒼天」発見(霧島演習場の外) 【事故・安全】 演習場外で発見・破損なし、原因と状況の確認が焦点
訓練中に行方不明となっていた汎用型ドローン「蒼天」1機が、演習場外で発見。破損はなく、他の被害も確認されていない。原因や当時の状況は確認中と報じられた。 https://news.yahoo.co.jp/articles/fdd4d60f6944a1d6ff92a259ae174ef92c254e00
<NEWS 4|注文導線を“LINEミニアプリ”に統一> そらいいな、五島市でドローン配送の注文をLINEミニアプリ化 【ビジネス/市場動向】 注文・支払いの利便性向上を前面に出し、ドローン配送の利用ハードルを下げる狙い
五島市内のスーパー・飲食店と提携し、惣菜・テイクアウトのドローン配送をLINEミニアプリ「注文くん」で受注開始。買い物利便性向上と地域の消費機会創出を目的に掲げ、提携店舗・配送エリア拡大やUI/UX改善も進めるとしている。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000175769.html
<NEWS 5|許認可・調整まで含めた“支援パッケージ”> ブルーイノベーション×文京区×JUIDA、災害時ドローン支援協定 【事故・安全】 「飛ばせる」に留めず、発災直後から実装レベルで動かす支援体制の構築を明示
3者が「災害時等のドローン支援活動」協定を締結。調査・情報収集・広報・物資運搬に加え、操縦者派遣、機体提供、許認可手続き、関係機関調整まで連携する。映像提供や、同一空域でのヘリとドローンの航空運用調整支援も想定している。 https://online.logi-biz.com/138761/
今月は、自治体の記念イベントでドローンの社会受容を広げる動きと、都市部での災害時物流ルートを想定した運用検証が並びました。一方で、訓練中の機体ロストと演習場外での発見が報じられ、安全面では逸脱時対応まで含めた運用管理の重要性が浮き彫りになりました。離島ではLINEミニアプリ化のように、利用導線の整備でサービスを日常に寄せる動きも進んでいます。 -
 2025-12-31
2025-12-312025年12月AIドローンニュース ―AIが厳選した国内ドローン最新トピック集―
<NEWS 1|許可・承認が“国家資格・機体認証”前提へ> 【2025年12月最新】「無人航空機 飛行許可・承認の審査要領」の改正をズバリ解説 【法規制/政策】 申請の“優遇ルート”終了で、運航体制の再設計が急務に。
バウンダリ行政書士法人が、12/18施行のカテゴリⅡ「審査要領」改正ポイントを整理して解説しました。これまで一部省略が可能だった「航空局HP掲載機」や「同掲載講習団体の民間資格」による優遇運用が見直され、今後は型式認証・機体認証、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)などを前提に、DIPS2.0での申請実務が変わる点が要旨です。運航側は“書類対応”に留まらず、機体要件・教育・記録(証跡)まで含めた標準化が求められます。 https://boundary.or.jp/aboutdrone/rule/4160/
<NEWS 2|ドローンドックで“毎日の見守り”を現実に> ドローンを活用した通学路安全見守り事業(千葉県 東庄町) 【事故・安全/自治体施策】 定常運用のノウハウが、他自治体展開の鍵になります。
千葉県東庄町が、町保有のドローン(DJI Matrice 4)とドローンドック(DJI Dock 3)を活用し、児童生徒の安全見守りに取り組みます。まずフェーズ1として学校敷地内で、安全性や運用体制(飛行頻度、監視手順、緊急時対応など)を検証し、将来的に通学路へ段階的に範囲を広げる計画です。ドローンドックの強みである「定点・自動・継続」を日常領域に持ち込む試みで、地域受容性や体制設計の“型”づくりが注目点です。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000131865.html
<NEWS 3|変電所点検が“巡回から自動化”へ> Skydio Dock for X10で自動巡視点検を実証(KDDIスマートドローン×四国電力送配電) 【社会活用/産業応用】 ドック×自動飛行が、点検の省人化を現場レベルで押し上げます。
KDDIスマートドローンと四国電力送配電が、香川県の讃岐変電所で自動充電ポート付き「Skydio Dock for X10」を用いた自動巡視点検を実証しました。変電所は構内が複雑で電波環境・安全確保も難しい領域ですが、飛行ルートの工夫などにより安定した自動飛行と、設備・計器類の自動撮影が可能であることを確認。点検の省人化・効率化に向けた運用知見を獲得したとしています。次は、検知精度(異常兆候の拾い上げ)と、保全業務フローへの組み込みが焦点になりそうです。 https://kddi.smartdrone.co.jp/release/10310/
<NEWS 4|“空の次”は海中へ> FullDepth:シリーズDで総額9.5億円の資金調達を完了 【ビジネス/市場動向】 水中インフラDXが加速し、AUV化が競争軸になっていきます。
国産水中ドローンを手がけるFullDepthが、シリーズDで総額9.5億円の資金調達を完了したと発表しました。水中インフラの点検・調査は人手とコストがかかり、安全面の課題も大きい領域です。同社は、水中インフラのデジタル化を進めるとともに、将来の自動化・自律化(AUV化)に向けた研究開発を加速するとしています。空のドローンで進んだ「省人化→自動化」の流れが水中にも波及する形で、公共インフラ保全やエネルギー分野での実装期待が高まります。 https://fulldepth.co.jp/news/300
<NEWS 5|“測って、再現して、認証を速くする”> 東京大学とドローン性能計測技術の共同研究を開始(ASTOM R&D×東大) 【技術/研究開発】 計測データ起点のモデル化が、開発と審査の両方を効率化します。
ASTOM R&D社と東京大学が、ドローンの性能計測システムおよびドローンシミュレーターの共同研究を開始しました。実機の飛行・挙動データを精密に計測し、その結果をもとに機体の高精度モデル化を進めることで、設計段階から仮想環境で性能・安全性を検証する“フロントローディング”を狙います。さらに、審査・認証に必要な説明や試験の効率化(再現性ある根拠提示)にもつなげる方針です。国産機や新規機体の事業化では「評価の仕組み」自体がボトルネックになりがちなため、基盤技術として注目されます。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000078688.html
許可・承認の審査要領改正により、DIPS申請は国家資格・機体認証を軸に運用を組み直す流れが強まりました。点検ではドローンドックによる自動巡視が現場適用に近づき、自治体は通学路見守りなど“日常領域”へ拡大。研究面では計測×シミュレーションで認証効率化を狙う動きが目立ちます。 -
 2025-11-30
2025-11-302025年11月AIドローンニュース ―AIが厳選した国内ドローン最新トピック集―
<NEWS 1|大規模火災の鎮火判断を“空から支える”> 大分市佐賀関でドローン熱源調査が継続 【事故・安全/防災】 被災地の鎮火判断と住民の生活再開を支える科学的モニタリング。
大分市佐賀関の大規模火災は、発生から10日以上が経過した今も飛び火した無人島で熱源が残存。大分大学などのチームが赤外線カメラ搭載ドローンで上空から熱源を特定し、再燃リスクを評価しています。半島側では熱源がほぼ確認されず、今後は調査結果を踏まえた鎮火判断や、立ち入り・通行許可証の発行を通じた生活再建が進められる見通しです。 https://tosonline.jp/news/20251127/00000010.html
<NEWS 2|「知らなかった」では済まない時代へ> 皇居敷地内でドローン飛行、外国人観光客を事情聴取 【事故・安全/法規制】 インバウンド時代のルール周知とリスクコミュニケーションが課題。
11月27日午後、皇居の敷地内上空で小型ドローンの飛行が確認され、皇宮警察本部が機体を回収。操縦していたとみられる外国人観光客2人から任意で事情聴取が行われました。皇居周辺は小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止エリアで、2015年の官邸ドローン事件を受けて厳しく規制されている区域です。観光客は規制を把握していなかった可能性が指摘されており、重要施設周辺における多言語でのルール周知や、抑止・検知体制の強化が改めて求められています。 https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014988161000
<NEWS 3|“音に頼らない防災”を実践> 聴覚障がいサーファーを守る避難誘導ドローンを実運用 【防災/社会活用】 誰も取り残さない防災インフラとしてのドローン活用が前進。
千葉県白子町で開催された「ワールドデフトリプルSゲームズ2025」のデフサーフィン世界大会で、聴覚障がいアスリートの安全確保を目的とした「避難誘導ドローン」が実運用されました。DJI Matrice 4TDにAI人物検知、高光量の赤色ライト、スピーカーを搭載し、5人のパイロットが2人1組で巡視。サイレンが聞こえない参加者に対して視覚的な避難誘導を行える体制を構築し、自治体・警察・レスキュー団体と連携した“視覚型防災”の有効性を検証しました。 https://www.fnn.jp/articles/-/962375
<NEWS 4|万博警備を見据えた運航管制> JAXAらがDOERシステムの有効性を実証 【社会インフラ/運航管理】 有人機・ドローンを束ねる“空の交通管制”の社会実装に一歩。
JAXAはウェザーニューズ、NTTデータ、Terra Droneと連携し、大阪・関西万博の会場を想定した実証で、有人機とドローンを統合管理する「DOERシステム」の有効性を検証しました。既存の災害救援ネットワークD-NETを発展させ、会場近くに模擬「運航調整所」を設置。飛行前日の調整から当日の監視、突発的な緊急任務の有人機・無人機への割り当てまでをシナリオで確認し、大規模イベント警備においても安全かつ効率的な運航管理が可能であることを示しました。 https://www.jaxa.jp/press/2025/11/20251107-1_j.html
<NEWS 5|クマ出没対策に“非致死的ドローン”> 岐阜県がツキノワグマ追い払いで活用へ 【防災/自治体施策】 人とクマの距離を保つ「空からの追い払い」という新アプローチ。
岐阜県は、令和7年度のクマ出没件数が前年を大きく上回り、人的被害も増えていることを受け、関係団体や猟友会と連携してドローンによるツキノワグマの追い払いを新たに実施すると発表しました。人的被害が発生した高山市・中津川市・飛騨市・白川村などの生活圏周辺から奥山側へ向けてドローンを飛行させ、クマが嫌がる音(犬の鳴き声など)や動物駆逐用煙火を用いて山側へ戻す計画です。使用機数や飛行ルートは現地確認のうえ調整し、住民の安全確保とクマの生息を両立する「非致死的な被害軽減策」として位置づけられています。 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/471858.pdf
今月は、大分の大規模火災での熱源調査や、デフサーフィン大会での避難誘導ドローン、万博警備を想定したDOERシステム、クマ対策など、「守るためのドローン」が一気に存在感を増した印象です。一方で皇居での違法飛行のように、一般ユーザーの裾野拡大にルール周知が追いつかない面も露呈しました。防災・警備・野生動物対策といった公共分野での実装が進むほど、インバウンドを含む利用者教育と、運航管理システムによる安全確保の両輪がますます重要になっていきます。 -
 2025-10-31
2025-10-312025年10月AIドローンニュース ―AIが厳選した国内ドローン最新トピック集―
<NEWS 1|都市近郊でレベル3.5配送へ> 和歌山市で日本初のDID含む実証を発表 【社会活用/産業応用】 都市圏でのコスト最適な配送モデル検証に期待。
和歌山市とNEXT DELIVERYが、これまで非DID限定だったレベル3.5をDID地区を含むルートで日本初実証へ。宇都宮病院—道の駅四季の郷公園の約4kmを遠隔運航し、11/4実施予定として都市近郊での低コスト運用可能性を検証すると発表しました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000115515.html
<NEWS 2|常設ポート×遠隔運航> 能登でAIドローン常設・広域リモート運航に成功 【社会活用/産業応用】 “常時稼働型”の地域運用に向けた一歩。
KDDI/KDDIスマートドローンが能登の公共施設4か所にドローンポートとAIドローンを常設。東京・北海道から4機を遠隔運航し、3Dモデリング撮影、橋梁点検、地震想定の被災確認を実施。常設拠点と遠隔の組み合わせによる全国展開を見据えます。 https://kddi.smartdrone.co.jp/release/9459/
<NEWS 3|「違法飛行」対策を本格議論> 警察庁が初会合、重要施設周辺の見直しなど 【法規制/政策】 実効性強化へ。運航者は動向の継続ウォッチを。
警察庁は10/7、「違法なドローン飛行対策に関する検討会」初会合を開催。重要施設周辺の飛行制限(いわゆるイエローゾーン)の見直しや、罰則・対処措置の在り方を議題に、制度改正に向け論点整理を進める方針が示されました。 https://www.sankei.com/article/20251007-WGLMJ2E66VKJXIB6BGLNKYLFEA/
<NEWS 4|小学生が測量×ドローン体験> 山口・長門市の出前授業で職業観育む 【教育】 学校現場での体験機会が裾野拡大に寄与。
長門市立俵山小で企業による出前授業を実施。グラウンドに描いた図形や校章をドローンで空撮し、最新の測量機器と合わせて体験しました。児童24人が土木・測量の仕事に触れ、地域と学校の連携強化にもつながったと報じられています。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2206647
<NEWS 5|復興願う500機の演出> 和倉温泉で大規模ドローンショー 【文化・エンタメ】 “見るドローン”が地域の士気と賑わいを後押し。
能登半島地震からの復興を願い、七尾市・和倉温泉で500機のドローンショーを実施。「復興」の文字や図柄が夜空に描かれ、住民や観光客が見守る中で地域の一体感と集客効果に貢献したと伝えられています。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mro/2238615
今月は運用面で都市近郊のレベル3.5実証や常設ポート×遠隔運航が進み、現場実装が一段と具体化しました。教育・地域イベントでの活用も広がり、市民の接点が増えています。違法飛行対策の議論も始まり、社会実装とルール整備が並走する流れが続きます。 -
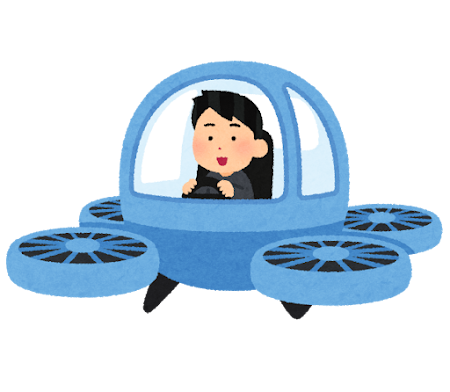 2025-09-30
2025-09-302025年9月AIドローンニュース ―AIが厳選した国内ドローン最新トピック集―
<NEWS 1|25kg以上は保険義務化へ> 10/1以降の新規申請で第三者賠償保険の加入が必要に 【法規制/政策】 大型機運用の前提条件が明確化。早めの保険整備を。
国交省は2025/10/1以降に新規で飛行許可・承認を申請する総重量25kg以上の無人航空機について、第三者賠償責任保険の加入を求めると周知。申請書への保険記載義務に加え、飛行時の付保状況と有効期間の確認も明示しました。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
<NEWS 2|万博で運航管理を試験提供> ドローン×空飛ぶクルマの状況把握を一元化 【社会活用/産業応用】 実運用下でのUTM/SDSP連携検証。制度実装に前進。
Intent Exchange・NEC・NTTデータが大阪・関西万博の会場内外で運航状況を一元把握するシステムを試験提供。8/16~10/13に運用性とStep2相当機能を検証し、その知見をUSP認定制度などの議論へ反映するとしています。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001051.000078149.html
<NEWS 3|大規模ショーで地域集客> 水都くらわんか花火でTDRスペシャルドローンショー実施 【社会活用/産業応用】 大規模ショーが地域集客に寄与。安全運用が鍵。
9/21の「水都くらわんか花火大会」で東京ディズニーリゾートのドローンショーを初実施。総計約1,500機が約15分でキャラクターを描き、来場は約30万人で過去最多と報じられました。 https://www.lmaga.jp/news/2025/09/970225/
<NEWS 4|津波避難広報ドローンが自動稼働> 千葉県一宮町で運用、職員を危険にさらさず状況確認 【社会活用/産業応用】 防災DXの象徴。沿岸自治体での横展開に期待。
一宮町でJアラート連動の津波避難広報ドローンが稼働。7/30の注意報~警報下で自動離陸し、海岸での避難呼びかけと映像による状況確認を実施。職員の現場立ち入りを減らし、即応性を高めた事例です。 https://news.yahoo.co.jp/articles/71c2db0e914687bc5e25bdb553f98146e270980a
<NEWS 5|インフラ点検のDX> ドローン下水道点検の最新技術実証 【技術/製品】 危険作業の代替に有望。自治体連携と普及に期待。
DRONE SPORTSが狭所点検用「Rangle micro」と地下通信中継「Rangleエクステンダー」で下水道点検を実証。直径1.5〜3.0mの管やチャンバーで遠隔点検を行い、画像精度・飛行距離・安全性の向上を確認しました。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000033439.html
今月は制度面で25kg以上機の保険義務化が明確化し、運用の前提条件が整備されつつあります。万博ではUTM/SDSP連携の実運用検証が進み、運航管理の具体化が前進しました。加えて、自治体の防災ドローン稼働や下水道点検の実証など社会インフラでの実装が広がりました。イベント分野の大規模演出も定着し、裾野が着実に広がる月でした。 -
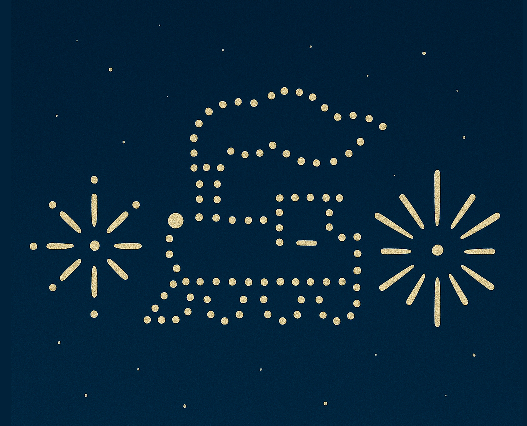 2025-08-31
2025-08-312025年8月AIドローンニュース ―AIが厳選した国内ドローン最新トピック集―
<NEWS 1|レベル3×ドックで定常運用へ> KDDIスマートドローンら、レベル3遠隔自動測量を1年間継続運用に成功 【社会活用/産業応用】 ドック常設×遠隔で建設の省人化が現実に。横展開に期待。 建設現場に自動充電ドック付きドローンを常設し、補助者なし目視外(レベル3)で週次の遠隔自動測量を1年間継続。KDDIスマートドローン、Liberaware、大林組が国内初として発表し、定常運用の実効性を示しました。 https://kddi.smartdrone.co.jp/release/9144/
<NEWS 2|“撮ってから構図”の新体験> Insta360新ブランド「Antigravity」A1を発表 【技術/製品】 個人クリエイターの撮影スタイルを刷新。軽量×8Kで裾野拡大。世界初の8K 360度撮影に対応する「Antigravity A1」を発表。フリーモーションテクノロジーとVisionゴーグル、Gripコントローラーで直感的な没入型飛行、249gで多くの国や地域で登録不要。編集時に自由にリフレーム可能、2026年1月に世界同時発売予定。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000052813.html
<NEWS 3|都心の空に“演出”を実装> JR東日本、高輪ゲートウェイで都市型ドローンショー 【社会活用/産業応用】 都市のど真ん中で実施。安全運用と社会受容の確認に意義。 8/23、TAKANAWA GATEWAY CITYで約10分×2回のドローンショーを実施。300機が高さ40〜60m(最大80m)で汽車や山手線、ロゴ、花火などを描写。招待客や通行人が鑑賞し、都市空間での見せ方を実証しました。 https://dronetribune.jp/articles/25326/
<NEWS 4|“データ収集”をサービス化> Qlean Dataset、企業向け「ドローン空撮データ収録」を開始 【ビジネス・市場動向】 “欲しいデータだけ”を手軽に取得。AI活用の下支えに。 Visual Bankの「Qlean Dataset」が企業ニーズに応じた空撮データ収集サービスを開始。現地で必要データを撮影し、AI/解析向けのデータ整備を支援。データ取得の外注化で業務DXを前進させます。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000108024.html
<NEWS 5|官民からの信頼を獲得> Terra Drone、日本スタートアップ大賞2025で国土交通大臣賞 【ビジネス・市場動向】 公的評価で信頼感増。事業拡大と海外展開の弾みに。 Terra Droneが経産省主催「日本スタートアップ大賞2025」で国交大臣賞を受賞。測量・点検やUTMなどの実績と社会課題解決への貢献が評価され、官邸で表彰式が行われました。 https://terra-drone.net/23258
今月は現場実装と体験価値が同時に進みました。建設分野ではレベル3の継続運用が定常化の道筋を示し、都心のドローンショーが一般層の関心を押し上げました。個人向けの新機や空撮データのサービス化も登場し、民間での活用が加速。官民の評価も追い風となり、裾野拡大が着実に進んだ月でした。

